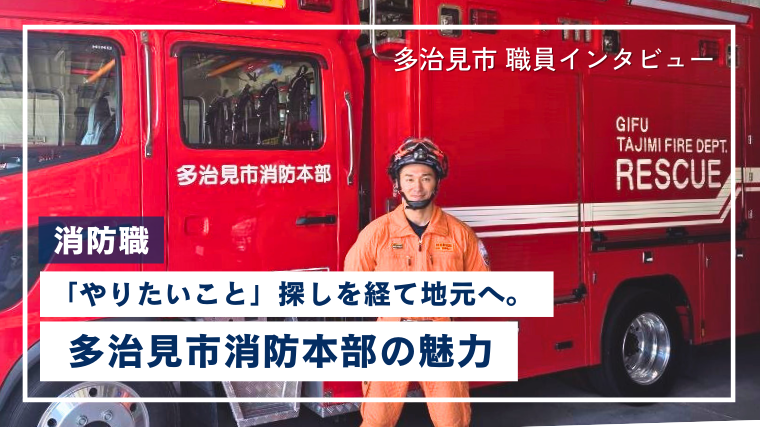多治見市消防本部で働く片岡さんのインタビュー記事です。入庁の経緯や、火災よりも救急対応が多いという現場のリアル、そして「若手がいきいきしている」と評される職場の雰囲気や、充実したキャリア形成支援制度について語っていただきました。
ーまずは、片岡さんのこれまでのご経歴を教えて下さい。
片岡:多治見市の出身です。大学ではスポーツに打ち込み、卒業後はすぐに就職せず、アルバイトをしながら3年間、自分のやりたいことを探す期間を設けました。
色々な場所を訪れる中で、最終的に「地元に戻りたい」という気持ちが強くなり、多治見市消防本部を志望しました。2021年に入庁し、今年で5年目になります。
―改めて、地元が良いと思われたんですね。
片岡:色々な場所を見てきた中で、やはり自分は都会の喧騒が合わないなと感じました。かといって、何もない田舎というわけでもなく、適度に都会の便利さがありながら、豊かな自然も残っている多治見という街が、自分にとっては一番しっくりくる「ちょうどいい街」だと再認識しました。
そこで地元に戻ることを決め、次にどんな仕事がしたいかを考えました。学生時代にラグビーをやってきた経験から、チームワークを大切にしながら、自分の体力を活かせる仕事がいいなと。そして「人のためになりたい」という思いもありました。その全てを満たせるのは消防士という仕事だと考え、多治見市消防本部への入庁を決めました。
ー入庁後はまず消防学校に入られると思いますが、その後、現場に配属されてからの教育体制について教えてください。
片岡:消防学校を卒業して現場に戻ってくると、まず最初の1か月間は、救急車に乗務できるようになるための訓練を集中的に行います。多治見市消防では、消防隊と救急隊が専属で分かれているわけではなく、全員が消防車にも救急車にも乗務します。
特に、日々の出動件数は火災よりも救急が圧倒的に多いので、まずは救急隊員として3人一組で活動できるレベルになることが求められます。この最初の1か月間で必要な知識と技術を習得し、救急隊員として認められて初めて、現場の一員としてカウントされるようになります。
ー多治見市消防本部の組織体制について教えてください。消防署は市内にいくつかあるのでしょうか。
片岡:市内には南消防署、北消防署、笠原消防署の3か所があります。私が今所属している南消防署が本部機能を持っていて、指令課や総務課、予防課といった日勤の部署も併設されています。職員数や車両の規模も南が一番大きく、オレンジ色の服を着た特別救助隊も南に配属されています。その次に北、そして笠原という規模感です。私は最初の4年間は北消防署にいて、今年度から南消防署に異動してきました。
ー勤務体制はどのようになっていますか。
片岡:多治見市消防は2交代制勤務です。14日間を1サイクルとして、「当務→非番→当務→非番→休み→休み」と、「当務→非番→当務→非番→当務→非番→休み→休み」という2つのパターンを繰り返していきます。
勤務時間は朝8時半から翌朝の8時半までの24時間です。1つの班は、最低でも12人、多い時で14人ほどの体制で動いています。
ー24時間勤務の中で、担当する業務はどのように分かれているのですか。
片岡:大きく分けて「警防担当」「救急担当」「予防担当」があり、その他に庶務や防災などの担当もあります。基本的には年度ごとに担当が決まっていて、私は今年、予防担当です。
警防担当は、日々の車両や資機材の点検・管理が主な業務です。それに加えて、1日のどこかで警防訓練を計画し、隊員全員で実施します。
救急担当は、救急出動後の報告書作成や、救急訓練の企画・実施を担います。この担当は、基本的に「救急救命士」の資格を持っている職員が務めます。
そして、私が今担当している予防担当は、市民の方や事業者から提出される書類の処理や、事業所への立入検査などが主な仕事です。
ー片岡さんご自身は、これまでどのような担当を経験されてきたのですか。
片岡:1年目と2年目は警防担当、3年目に予防担当、4年目は再び警防担当を経験し、5年目の今年、また予防担当になりました。救急救命士の資格を持っていないので、これまでは警防と予防の二つを経験してきた形ですね。

ー多治見市消防本部ならではの特徴や、働きやすさにつながるポイントがあれば教えてください。
片岡:まず、先輩方からよく聞くのは「多治見市は大きな災害が少ない」ということです。これは、市民の皆さんにとっては非常に良いことですし、私たちにとっても誇れることだと思います。
次に、医療体制が充実している点です。市内には地域の中核を担う大きな病院があり、救急搬送がスムーズに行えます。心肺停止といった一刻を争う傷病者も迅速に搬送できる体制は、救命率の向上にも繋がっており、消防活動を行う上で非常に心強いです。この病院とは定期的に消防側と病院側で会議を開き、意見交換をしています。お互いの視点から意見を出し合うことで、より良い連携体制を築けていると感じます。
そして、働く環境の面で言うと、来年度から北消防署が新庁舎になるのですが、それに伴い仮眠室が個室になる予定です。これまでは広い部屋で雑魚寝のような形だったのですが、プライベートな空間が確保されるようになります。
24時間という長い勤務の中で、しっかりとリラックスできる個室が用意されるのは、心身のコンディションを整える上でありがたい改善ですね。
ー実際に消防士として働いてみて、入庁前に抱いていたイメージとのギャップはありましたか。
片岡:消防士というと、やはり火災現場で消火活動をするイメージが強かったのですが、実際に入ってみると、出動の9割方は救急で、火災は1割程度です。これは大きなギャップでした。
ーでは、仕事のやりがいを感じるのはどのような瞬間ですか。
片岡:やはり市民の方から「ありがとう」と感謝の言葉をいただいた時は、素直に嬉しいですし、この仕事をしていて良かったなと感じます。
また、先日の勤務でもあったのですが、子どもたちが庁舎見学に来てくれるんです。消防車をキラキラした目で見つめる子どもたちの姿を見ると、大きな誇りを感じます。
ー5年間働かれる中で、特に印象に残っている経験はありますか。
片岡:昨年の能登半島地震の際に、緊急消防援助隊として被災地に派遣された経験は忘れられません。十分な睡眠時間も取れない中、朝から暗くなるまで、ひたすら要救助者の捜索活動を続けました。もちろん、肉体的にも精神的にも大変な現場でしたが、消防士としての使命感を改めて強く認識しました。
これから起こると言われている南海トラフ地震など、大規模災害が発生すれば、消防士は休みなく活動することになると思います。これから消防士を目指す方には、そうした厳しい側面も理解した上で、この仕事に誇りを持って入ってきてほしいなと思います。
ー今後のキャリアプランについて、考えていることはありますか。
片岡:入庁当初は火災現場で活躍したいという想いが強かったのですが、先ほどお話ししたように、日々の業務のほとんどは救急です。その現実に直面し、活動する中で、今は救急分野の専門性を高めたいという気持ちが強くなっています。
幸いにも、多治見市消防本部には、働きながら救急救命士の資格取得を目指せる「内部養成制度」があります。私もその制度を利用して、2年後に東京の養成所に半年間通うことが決まっています。そこで学び、国家試験に合格して、救急救命士として現場でさらに貢献できるようになりたいです。
また、今年から南消防署に異動し、特別救助隊にも所属することになりました。交通事故で車内に閉じ込められた人の救出や、崖からの転落事故など、特殊な知識と技術が求められる現場に出動する部隊です。
消防や救急とはまた違う形で人の命を助けることができる、非常にやりがいのある任務だと感じています。今後は、救急救命士としてのスキルと、特別救助隊員としてのスキルの両方を高め、どんな現場でも対応できるプロフェッショナルになるのが目標です。

ー職場の雰囲気はいかがですか。職員同士の関係性などについて教えてください。
片岡:これは自信を持って言えるのですが、多治見市消防本部は近隣の消防本部に比べて、離職率が低いと感じます。実際に働いてみても、職員みんな本当に仲が良く、すごく働きやすいです。
消防というと、体育会系の厳しい上下関係なども耳にすることもありますが、多治見ではそういった理由で辞めていくという話は聞いたことがありません。もちろん、人命に関わる仕事なので規律や厳しさはありますが、理不尽なものではなく、非常に風通しの良い組織だと思います。
近隣自治体の消防本部と交流している中でも、若い職員が生き生き働けているといっていただけています。自分たちだけでなく、客観的に見てもそう映っているというのは嬉しいですね。
ーワークライフバランスについてはいかがですか。
片岡:休みはもともと多いですし、年次有給休暇を使えば、5連休といった長期休暇も気軽に取れます。職員同士で勤務を交代することも可能なので、かなり柔軟に休みを調整できる環境です。旅行好きには最高の職場だと思います。
また、祝日に勤務すると「祝日勤務手当」が支給されます。他の消防本部では、祝日勤務を代休扱いにするところもあると聞きますが、給与にプラスされるので、ありがたいですね。逆に、その祝日に休みたい場合は、手当が出ない代わりに年休を消費せずにお休みすることも可能です。
ー本日はありがとうございました。
取材・文:パブリックコネクト編集部(2025年5月取材)