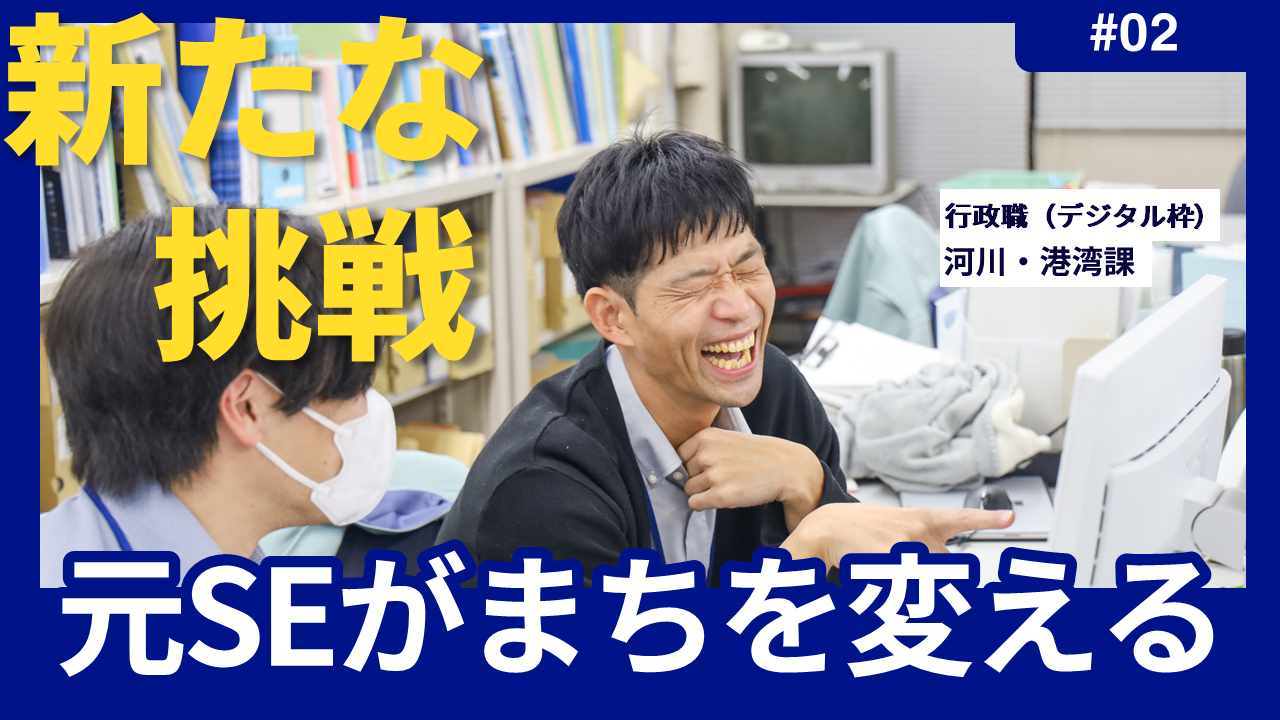富山県射水市役所で働く井村さんにインタビューしました。システムエンジニアから、行政のデジタル枠として市役所に転職したという異色の経歴を持つ井村さん。行政におけるDXの可能性、そして地域活性化への熱い思いについて伺いました。「市役所はヤバイ!」と語る井村さんの挑戦から、地方公務員というキャリアの新たな魅力を覗いてみませんか?
―入庁するまでのご経歴を教えていただけますか?
井村:大学院卒業後、東京のシステム会社にシステムエンジニアとして入社し、約11年間にわたり電子カルテの開発などに携わってきました。システムの開発から運用・保守まで、トータルでのサポート業務を経験しました。その後、令和4年度に射水市役所へ転職しました。
―11年間勤めた民間企業から転職された理由はなんですか?
井村:転職のきっかけは、妻が富山県出身でUターンを考えていたことでした。「まあ、富山に行くのもいいかな」という軽い気持ちでの転職でしたし、東京にこだわる理由も特になかったんです。どうせ行くなら、これまでとは違う世界に飛び込んでみようと思っていたところ、市役所で“デジタル枠”の募集があることを知りました。義父の後押しもあって、射水市役所に応募してみた――というのが経緯です。実は、妻も射水市にはほとんど行ったことがなかったので、特別な思い入れがあったわけではなく、本当にノリで応募したような感じですね(笑)。
民間でも同じようなIT系の仕事ができる会社はありましたが、正直あまり興味がなかったので受けませんでした。
行政の仕事については全く知らず、当時は「昔ながらの堅いお役所仕事」というイメージしか持っていませんでした。市町村の選び方にも特にこだわりはなく、選考回数が少なく時期も早かったため、「とりあえず受けてみよう」と思ったのが受験のきっかけです。ただ、今振り返ると、その選択が結果的に良い方向につながったと感じています。
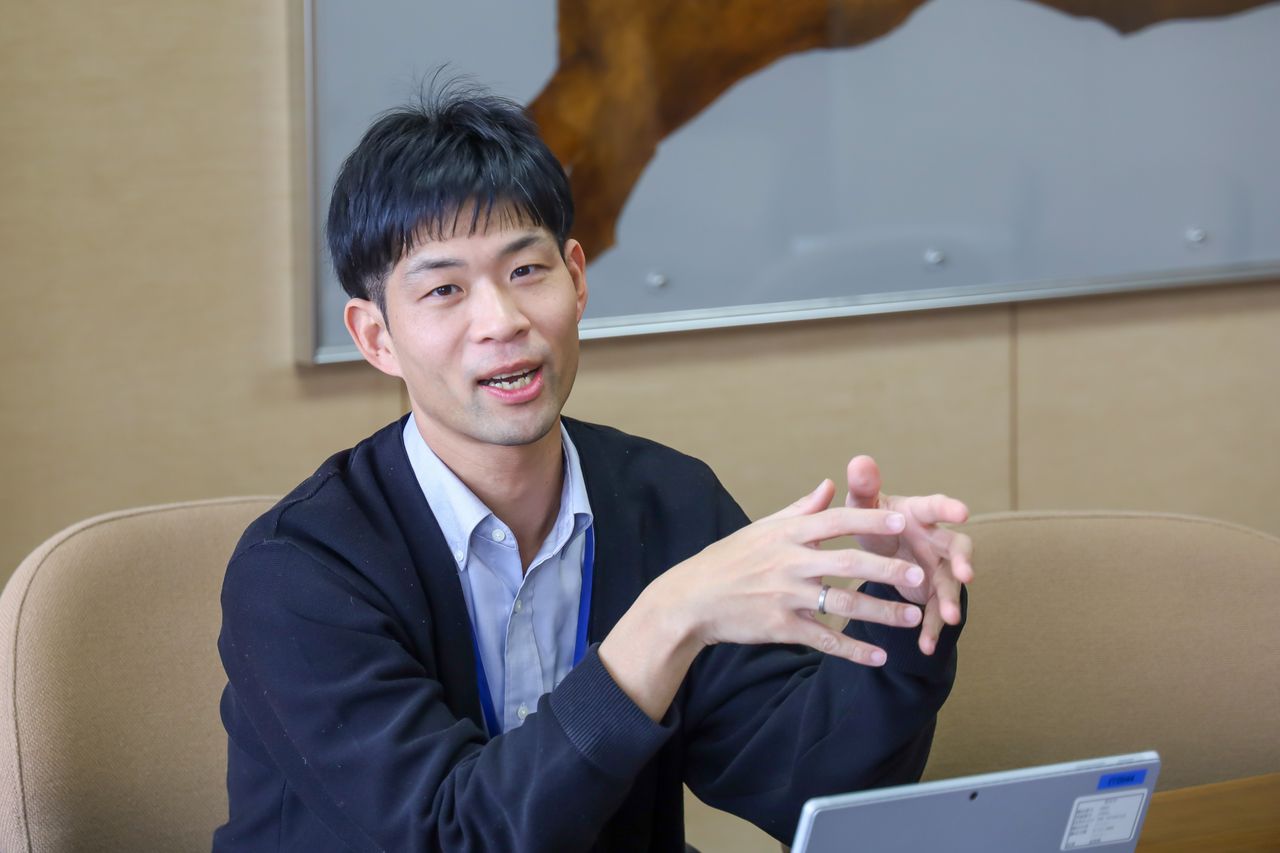
―実際に入庁されてからどのような仕事を担当されたのですか?
井村:最初の2年間は、地域福祉課と未来創造課DX推進班を兼務していました。私は行政職ではありますが、デジタル分野の知見を持つ人材枠(いわゆる「デジタル枠」)で入庁したため、このような兼務体制となりました。ちなみに、この枠での採用は私が初めてだったようです。
地域福祉課では、高齢者向け在宅サービスとしての車いすタクシーや移送サービスの助成金交付業務、公共施設の管理など、非常に幅広い業務を担当しました。業務を通じて福祉の知識は身につきましたが、最後まで私は福祉にまったく興味が湧きませんでした(笑)。
それでも仕事を続けられた理由は、この職場が本当に素晴らしい環境だったからです。周りの方々が優しく、上司も理解があり、恵まれた職場だったと思います。もちろん甘やかされることはなく、お互いが助け合い、意見を言い合える環境があったことが良かったです。ある意味、私自身が「福祉の心」で育ててもらっていたのかもしれません。そんな中で、「この人たちのために何か貢献したい」という帰属意識が自然と芽生え、仕事を頑張れたと思っています。
2年間で業務の大枠を把握し、「さあ、これから改善していこう!」と思った矢先に異動が決まりました。市役所ではよくあることですが、やはり少し寂しかったですね。
一方、DX推進班としては「健康管理」をテーマに、市民にスマートウォッチを装着してもらい、収集したデータを富山県立大学と連携して分析し、今後の施策に活用する実証実験に携わっていました。射水市には「6つのDXビジョン」があり、その中の一つである健康管理分野を、私がまず担当することになったのです。
しかし、この事業については十分な成果を出せたとは言い難く、私が関わったのはデータ収集の段階まででした。産学官連携の難しさや、行政としてプロジェクトを前に進めていくことの難しさを、身をもって実感した経験でもあります。
―現在はまた違うお仕事をされているんですね。
井村:地域福祉課から異動し、現在は河川・港湾課と未来創造課DX推進班を兼務しています。ただ、現在は大島分庁舎という別の庁舎に配属されていることもあり、業務の中心は河川・港湾課に比重を置いています。主な業務は、海老江海浜公園や海王丸パークといった公共施設の維持管理・運営です。施設の維持管理を行いつつ、より多くの人が訪れたくなるような賑わいを創出し、魅力ある場所として地域の活性化につなげていけたらと考えています。

―そうなんですね。
井村:地域福祉課で担当していた公共施設とは異なり、港湾や海岸は県が管理者であるため、調整が必要となり、物事を動かすハードルが一気に上がり、自分が実現したいことがなかなかできない壁を感じました。そこで、行政という立場にとらわれず、地域を盛り上げるために自分にできることはないかと考え、民間の方々と協力して「いみずのめ」という新たな任意団体を立ち上げ、活動を始めました。

―どのような団体なのですか?
井村:「いみずのめ」は、市役所職員の若手チームと一般社団法人「とやまのめ」がタッグを組んだ任意団体です。この団体はまちを面白くしながら地域貢献することを目指しており、その活動の一環として、今年の春に海老江海浜公園で「身投げサウナ」というサウナイベントを企画しています。
3月と4月は富山でホタルイカ漁のシーズンで、海岸にホタルイカが打ち上げられる「ホタルイカの身投げ」という現象が見られます。射水市もホタルイカの名産地として知られており、県外からも多くの方々が訪れます。しかし、射水市では地元が稼ぐ仕組みが十分に作られていないと感じていました。
そこで、民間の方々と話し合い、この海岸でできるイベント「身投げサウナ」を企画しました。海岸沿いにテントサウナを設置し、一番寒い時期の日本海に「身投げ」してもらい、最高のととのいを感じてもらうという内容です。
少し尖ったコンテンツではありますが、人々に強い印象を残すためには、それくらい目立つことが重要だと思いました。まずはやってみようということで、今、団体として取り組んでいます。
―珍しいですが面白い取り組みですね。
井村:行政っぽくはないと思います(笑)。ただ、市場に身を置いておかないと行政と民間に意識のズレが生じ、そこに壁ができてしまいます。その壁こそが、「面白いまちづくり」の障害になると感じています。そういった思いからこの団体を立ち上げましたが、この活動はあくまで私的なものであり、兼業申請を出したうえでやっています。仕事とは別に、まちづくりに携わることは大変ですが、庁内でも応援してくれる人がいて励みになっています。
上司の方々もとても理解があり、自ら考え、提案すればやりたいことを実現させてくれます。特に課長は協力的で、「どんどん新しいことに挑戦しろ!」と背中を押してくれる存在です。通常業務はきちんとこなしつつ、新しいことに挑戦できる風土は民間企業以上に自由度が高いと感じています。
ただ、受け身でいると何も変わらないので、自ら積極的に動くことが重要ですね。
―今後の計画もあるのですか?
井村:まだ始めたばかりの取り組みですので、まずは実績を一つずつ積み重ねていきたいと思っています。一緒に取り組む若い職員の方々にも、そうやって成果を出して実績を積み上げていく感覚を身につけてもらいたいです。その中で、仕事内外問わず、地域に貢献できる人材に成長していければと考えています。
地方は何もしなければ確実に縮小していきます。立ち行かなくなる前に、限られたリソースの中でも自分たちが動き、生き残る術を見つけていくことが非常に重要だと考えています。

―やりがいがある環境なんですね。
井村:やりたいことを実現できる環境だからこそですね。市を良くしたい、地域を盛り上げたいという思いももちろん大事ですが、私としては自分の成長につながることも高いモチベーションになっています。また、「いみずのめ」の取り組みが、海老江海浜公園に来る人を増やす事業だと考えると、それがそのまま本業の消費者向けや地域開発の事業企画につながるのではないかと思っています。
―最後に、どんな人に射水市役所に来てほしいですか?
井村:新卒の方には、射水市で何かをしたい、射水市というプラットフォームを使って自分のアイデアを実現したいという思いを持っている方が入るのが良いと思います。現在、採用市場は売り手市場ですし、自分がどう成長したいのか、何を得たいのか、どんな経験を積みたいのかで就職先を選ぶべきだと思います。射水市というプラットフォームを使って自分の何かを実現したいという思いがある方にとっては、まちづくりやその他の公共事業に携わることができる非常に良い環境です。
また、私と同じように転職してくる方には、射水市を本気で残したいと思ってくれる人、つまり危機感を持っている人と一緒に働きたいです。単純に安定していて定時で帰れると思っている人はいりません!地方都市としての射水市を良くしていかなくてはならないと本気で一緒に考えてくれる方に入ってきてもらいたいですね。
なぜ私がこのような思いに至ったかというと、「とやまのめ」の方々に出会ったからです。彼らは本気でまちづくりを行う有志の方々であり、一緒になにか事業に取り組んでいくことは非常に面白い経験です。このようなプレイヤーがどんどん出てくるまちにしていきたいと思っていますし、だからこそ自分もコミットできています。
東京や大阪などの大都市には、ヒト・モノ・カネでは勝てません。ですが、地域資源を磨き、尖ったコンテンツで勝負することができる。それができる方々と一緒に働いていきたいと考えています。
ー本日はありがとうございました
取材・文:パブリックコネクト編集部(2025年2月取材)