滋賀県愛荘町役場で働く青木隼人さんと大崎颯也さんのインタビュー記事です。お二人は現在、2025年9月〜10月に滋賀県内で開催される「国民スポーツ大会(国スポ・障スポ)」の推進室に専任担当として所属しています。
従来の公務員のイメージを覆すような企画力や創造性が求められる仕事のやりがい、そして若手職員の挑戦を後押しする愛荘町の風土について、等身大の言葉で語っていただきました。
ーまずはお二人の自己紹介と、これまでの経歴を教えてください。
青木:大学を卒業して新卒で入庁し8年目です。大学は県外でしたが温かい人間関係のある地元に帰って働きたい、貢献したいという気持ちが強く愛荘町役場を目指し、この4月から「国スポ・障スポ開催推進室」に所属しています。
大崎:私も大学卒業後すぐに入庁し5年目です。両親が公務員だったこともあり、自然と公務員を選択しました。昨年度から青木さんと同じく「国スポ・障スポ開催推進室」で勤務しています。
ーでは入庁してから経験された業務も教えてください。
青木:最初は税務課で、個人の住民税や固定資産税、法人の税金、そして徴収まで、一通りの業務を3年間でローテーションしながら担当しました。市民の方の生活に直結する非常に重要な仕事です。
その後、福祉課に異動となり4年間勤務しました。こちらでは、社会福祉協議会や民生委員の方々といった、地域の福祉を支える団体や人との連携が主な仕事でした。
大崎:私は最初の3年間、経営戦略課で職員の福利厚生に関する業務を主に担当していました。職員の保険の加入手続きなど、どちらかというと役場の内部向けの事務的な仕事が中心でしたね。住民の方と直接やり取りするというよりは、職員と向き合い、組織を内側から支える仕事です。
ー印象に残っている業務はありますか?
青木:福祉センターの中にある、町内でも比較的大きな公園を老朽化のためリニューアルし、老若男女、障がいの有無に関わらず、みんなが集える「インクルパークあいしょう」をオープンさせたことが一番印象に残っています。通常なら公園課やまちづくり課が担当するような事業だったかもしれませんが、福祉センターに付随する公園だったこともあり、福祉課の事業として進めることになりました。
もちろん、専門知識が必要な部分は他部署と連携しますが、主体となってプロジェクトを動かしていく経験は、大きなやりがいを感じましたね。
ーでは現在、お二人が所属されている「国スポ・障スポ開催推進室」とは、どのような部署なのでしょうか?
青木:今年(2025年)の10月に、滋賀県内で「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ2025」という国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会が開催されます。愛荘町はアーチェリー競技の会場になることが決まっており、推進室はこの大会を成功させるために設置された、教育委員会所属の専門部署です。
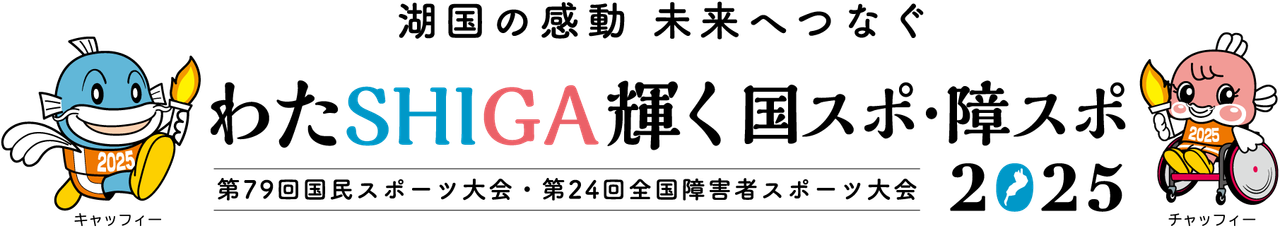
ーこのイベントは、昨年度だと佐賀で約50万人も来場されている一大イベントなんだそうですね!どのような体制で進めているのですか?
大崎:専任の担当者は、私たち二人だけです。その他に、室長補佐が一人と、他の業務と兼務している職員が約10名いるという体制です。
青木:私も昨年までは、福祉課の仕事と兼務でこの推進室の業務に携わっていました。
ー準備はいつ頃から始まったのでしょうか?
大崎:この推進室の前身となる「準備室」が立ち上がったのは令和4年度からです。令和4年度は栃木県、令和5年度は鹿児島県で開催された大会を視察し、どんな準備や運営をしているのかを学びました。
そして昨年、令和6年度にはリハーサル大会の準備を進め、私が専任担当として着任しました。当時は専任が私一人だったので、正直、最初は戸惑いましたね。
自分で考えて企画し、外部の人と調整していく仕事でしたので、今までの人事の仕事と正反対だなと。最初は言われたことをやるだけで、精一杯でした。
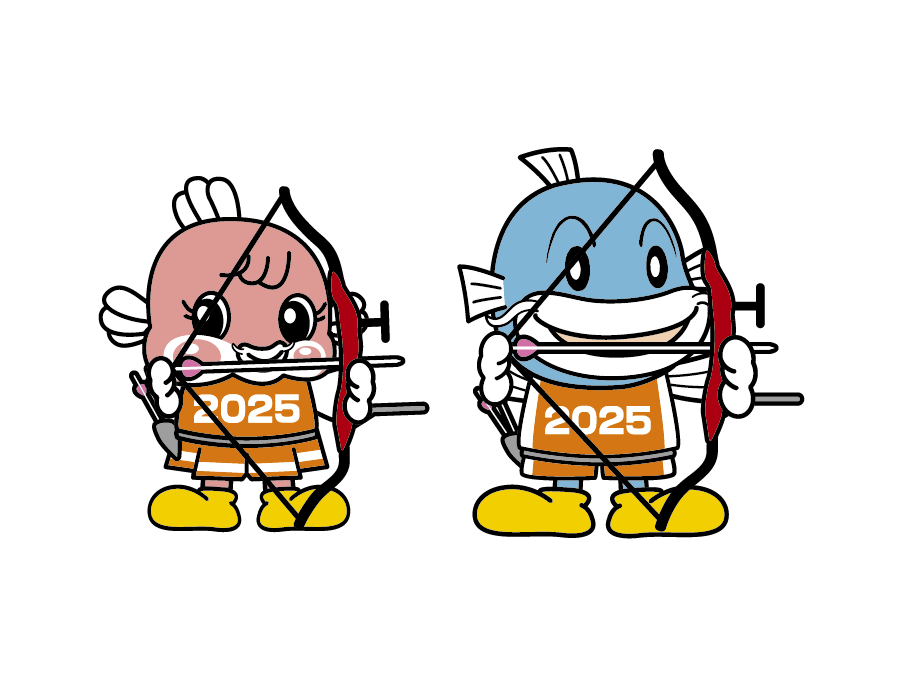
ーアーチェリー競技会の成功が求められるミッションなんですか?
青木:それだけであれば、そんなに難しくはありません。会場を手配し、専門業者やアーチェリー協会に運営を依頼すれば、大会自体は成り立ちます。
重要なのは、この機会を最大限に活かして、いかに愛荘町の魅力を全国にPRできるか。そして、大会後もこの経験を地域のスポーツ振興にどう繋げていくか。知名度アップや将来への投資といった、「見えづらい成果」をいかにして創出するかが、私たちに課せられた最大のミッションであり、最も頭を悩ませるところです。
ー具体的にどのような企画をされてきたのでしょうか?
大崎:例えば、町内の企業様を訪問して、協賛をお願いする活動も一つです。大会の趣旨を説明し、物品などのご提供をお願いしています。ご協力いただいた企業様の名前が入ったうちわやティッシュをイベントで配布することで、町全体で大会を応援している雰囲気を作っています。
また、大会当日に来場者の方々に楽しんでもらえるよう、町の観光スポットを巡るスタンプラリーを企画したり、愛荘町内で古くから作られ、滋賀県の伝統的工芸品に指定されている「愛知川びん細工手まり」をPRするブースをどう展開するかを考えたりしています。

青木:最近では、オリンピックの聖火リレーのような「炬火(きょか)イベント」というものも実施しました。滋賀県内の各市町で火を繋いでいくイベントなのですが、愛荘町では国宝である金剛輪寺を舞台に、住民の皆さんとともにリレー形式で実施しました。
歴史ある場所でイベントを行うことで、町の文化的な魅力も発信できたのではないかと思っています。その他にも、町の公式YouTubeチャンネルで、職員が出演するPR動画を配信しています。
あとは、大会時着用するTシャツなどのデザインも自分たちで決めました。本当に、ゼロから自由に発案でき、楽しく仕事ができています。
ー企画要素のある仕事は大変でしたか?
青木:すごく大変ではありますが、この部署だけが特別、ということでもないとは思っています。例えば私がいた税務課や福祉課でも、法律や条例という決まりはありますが、その中で「どうすればより良い住民サービスを提供できるか」「どうすれば住民の方々に喜んでもらえるか」を考える余地は常にありました。
公務員仕事と言えば「型どおり」のようなイメージを持たれるかもしれませんが、AIに代替されないようなオリジナリティやクリエイティブな視点が、どの部署でも必ず求められるようになると感じています。
そういう意味で、この部署での経験は、今後のキャリアにおいて間違いなく大きな財産になると確信しています。

ー大崎さんはいかがですか?異動当初は苦手意識があったとのことですが。
大崎:正直、最初はやばいなと思いました(笑)。自分で考えて企画するなんて、最も苦手な分野だと思っていたので。しかし、室長補佐や先輩である青木さんが本当に親身にサポートしてくださってわからないことは何でも聞けるし、一緒に考えてくれる。
そうやって一つひとつ乗り越えていくうちに、だんだん仕事の進め方がわかってきて、今では「楽しい」と感じられるようになりました。慣れてくれば、そして仲間がいれば、できるもんだな、と。
ー職場の雰囲気はいかがですか?
青木:年齢や経験に関係なく、意見を言いやすい雰囲気だと思います。私も、大崎くんの若い感性や意見はすごく参考にしています。「こういうデザイン、どっちがいいかな?」と聞くと、的確なアドバイスをくれたりするんですよ。
大崎:ありがとうございます(笑)。青木さんは本当に尊敬できる先輩で、仕事の進め方から細かい相談まで、何でも親身に聞いてもらっています。安心して仕事ができていますね。

ーいよいよ大会本番まであとわずかですが、今のお気持ちはいかがですか?
青木:楽しみでも不安でもない、というのが正直なところです。どちらかというと楽観的で、「あと3ヶ月しかないけど、どこまでやれるかな」という感じですね。このプロジェクトは、何をもって「成功」とするかの定義が曖昧な部分もあります。
だからこそ、まずは自分たちが、そして関わってくれる皆が楽しんでやれたら、それが一番かなと思っています。
大崎:私はやっぱり不安が大きいです。いよいよ本番が迫ってきたな、という緊張感があります。来場してくださる選手や観客の皆さんに満足してもらえるか、無事に終えられるか、最後まで気は抜けません。
ーどのようなイベントにしていきたいですか?
青木:スタンプラリーの他にも、今後のスポーツ振興に繋がるような体験コーナーを企画しています。例えば、バスケットボールのスリーポイントシュートや、ストラックアウトのようなゲームに挑戦してもらい、クリアできたら町の特産品や大会の景品が当たるガチャガチャができる、といったものです。
そこで子どもたちが楽しいと感じてくれたら、地元のスポーツ少年団へと繋げていける。そうやって、大会を一過性のイベントで終わらせず、未来のスポーツの担い手を育てるきっかけにしたいです。
ー本日はありがとうございました。
取材・文:パブリックコネクト編集部(2025年7月取材)



