沖縄県糸満市役所で働く上原さんのインタビュー記事です。
これまでに税や福祉、防災や介護など多岐にわたる部署を経験した上原さんに、これまでの多様な経験から得た気づきや、現在の業務で感じるやりがい、そして生まれ育った糸満市で働くことの魅力について、熱く語っていただきました。
市民に寄り添い、課題解決に向けて主体的にアクションを起こすという、公務員ならではのの仕事のやりがいが伝わる内容となっています
ーまずは自己紹介と、糸満市役所に入庁されるまでの経緯を教えてください。
上原:出身はここ糸満市です。高校までを糸満市で過ごし、大学は鹿児島県内の体育大学に進学しました。体育大学に進んだこともあり、元々は保健体育の教員を目指していて、大学の課程で教員免許も取得しました。ただ、就職先の選択肢としては、教員の他に消防職員や、行政職員も考えていましたね。
大学卒業後は糸満市役所で臨時職員として勤務しながら正規職員の採用試験を受けて、平成21年度に入庁しました。
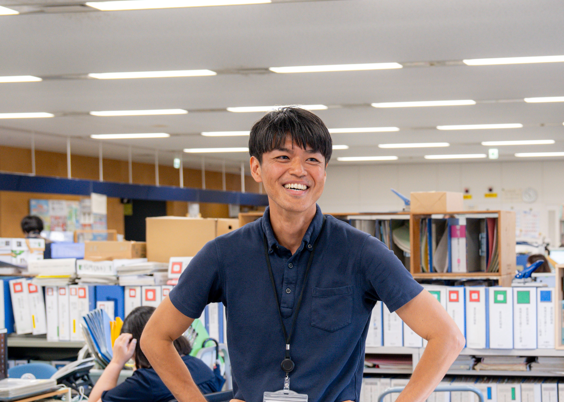
ー教員や消防ではなく、最終的に糸満市の行政職を選ばれた決め手は何だったのでしょうか?
上原:教員採用試験を受けていたのですが、当時はかなり狭き門でして…周りの先輩方もなかなか本採用に至らず、臨時職員として働きながら試験を受け続けているという状況を見ていて、行政職も視野に入れるようになりました。
消防職も受験をしていたのですが、周囲を見ていると実務経験豊富で「絶対消防士になる!」という強い意志を持って臨んでいた方ばかりでした。そんな中、自分がいざ消防士になったとしても、同じ土俵でやっていけるのか、と迷いが生じたんです。もちろん体を動かすのは好きだったのですが、言い方を変えるとそれ以外に明確な志望動機がありませんでした。
ちょうどその頃、臨時職員として市の行政に関わる中で、その仕事内容に強い興味を持つようになっていました。それで2年目は行政職を目指すことにして、無事採用に至りました。
ー糸満市で働くことを選ばれたのは、やはり地元だからでしょうか?
上原:そうですね、やはり家族が糸満市に住んでいますし、私自身も大学で一度県外に出ましたが、帰ってきたいという気持ちが強かったです。親も含め、これまで自分を育ててくれた人や地域に恩返しをしたいという気持ちもありました。
あとは、単純に糸満市の景色が好きなんです。もう故郷そのものというか、海の匂いとか、そういうものに囲まれている環境が好きで、このまちに直接貢献できる仕事がしたいという思いから、働くなら糸満市だと決めていました。
ー大好きな地元で働くというのはとても素敵ですね。入庁してから現在まで、どのような業務に携わられてきたのですか?
上原:最初に配属されたのは税務課の収納係で、市税の徴収を担当していました。国税徴収法という法律に基づいて徴収等を行う必要があるため、時には厳しい対応も求められる仕事でしたが、法律の枠組みや権限について深く学ぶことができました。
次に社会福祉課へ異動し、生活保護のケースワーカーを3年間務めました。こちらは税金の徴収とは全く逆で、支援を必要とする方に寄り添う仕事です。生まれたばかりの赤ちゃんからご高齢の方まで、文字通り人生に深く関わる経験をさせていただくことができました。
その後、秘書広報課に異動になったのですが、私の担当は秘書広報からはあまりイメージできない「統計担当」でした(笑)ちょうど5年に一度の国勢調査の年にあたり、その大きな調査を担当することになりました。
調査票の準備だけでも膨大な量で、調査員の確保や指導など、本当に多くの方々の協力なしには成し遂げられない仕事でした。統計データが様々な施策の根拠になることも学びましたし、分析手法なども身につけることができました。
次は総務課で防災担当を3年間経験しました。警報が出たらすぐに出勤して対応にあたる必要があり、気が抜けない毎日でしたね。台風はもちろん、トンガの噴火による潮位変動で夜間に発表された津波注意報の際も対応に追われました。そのほか、防災の各種計画策定に関する業務も経験することができました。
そして現在所属しているのが介護長寿課です。
ー本当に多岐にわたる部署を経験されていますね! 現在の介護長寿課では、どのような業務を担当されているのでしょうか?
上原:介護長寿課は4つの係がある比較的大きな部署なのですが、私は「高齢者支援係」に所属しています。他の係(管理係、認定給付係、包括支援係)が担当しない、いわば高齢者福祉全般に関する業務を幅広く担っています。
具体的には、介護保険適用外の在宅福祉サービス(外出支援やおむつ代助成、緊急通報システムなど)の提供、高齢者虐待への対応や身寄りのない方の保護措置、老人クラブへの支援、そして高齢者の介護予防事業などです。介護予防では、「通いの場」づくりとして、地域デイサービスや機能訓練施設の運営支援なども行っています。
また、前部署で防災担当を経験したことを活かして、災害時における要配慮者支援も担当しています。要配慮者支援と一言で言っても、その内容は福祉避難所の運営や避難行動要支援者名簿の作成、個別避難計画の推進など、盛りだくさんです。

ー現在の業務だけでも幅広いですね(笑)中でも特に力を入れていることなどはありますか?
上原:今、特に力を入れているのは、高齢者の介護予防のための「通いの場」づくりです。公民館での運動教室や機能訓練施設などがこれにあたります。糸満市では参加者が固定化したり、高齢化が進んで主体的な運営が難しくなっているケースが見られます。
そこで、今年度は「住民主体」の運営を目指して、より多くの高齢者が気軽に参加でき、かつ継続していけるような仕組みづくりに取り組んでいます。
また、広報誌などを活用して、「通いの場」の情報や介護予防に関する情報を積極的に発信し、まだ参加されていない方々への周知にも力を入れています。
これは、介護長寿課に来てから見えてきた課題を、昨年県のモデル事業などを活用して分析・検討し、4年目の今、ようやく具体的なアクションに移せている取り組みなんです。これまでの経験や知識、そして外部の知見も取り入れながら、課題解決に向けて主体的に動き始めたところなので、やりがいを感じますね。

ー糸満市役所で働く上でのやりがいや魅力は、どのようなところに感じますか?
上原:「市民のために働いている」という実感を得られることですね。先程お話ししたとおり、自分が課題だと感じていたことに対して、「こうなってほしい」という想いを形にし、それが少しずつでも実現に向かって動き出した時に、大きなやりがいを感じます。
もちろん、自分一人の力でできることには限りがありますが、周りの職員や関係機関、そして市民の方々と協力しながら、課題解決に向けて取り組んでいける環境があることが魅力だと思います。
また、余談にはなりますが頑張った後には庁舎の窓から見える美しい夕日が待っています(笑)この景色を見ながら、市民のために働けるということは、何物にも代えがたいですね。

ー全く異なる分野への異動も経験されているかと思いますが、人事異動についてはどのように感じていますか?
上原:3~4年周期で異動しているので、本当に多様な経験を積ませていただいていると感じます。これは市役所で働く魅力であり、幅広い視野を養う上で非常に有益だと思います。様々な部署の業務を知ることで、組織全体の動きや連携の重要性も理解できますね。
一方で、特定の分野を深く掘り下げたい、専門性を高めたいという気持ちも時には出てきます。例えば、私は健康運動指導士の資格を持っているので、介護予防の分野で体操メニューを作ったりもしていますが、これはあくまで一般行政職としての業務の一部です。自分が専門職として介護予防の分野にもっと深く関わることで、他にももっとできることがあるかもしれない、と思うこともあります。
ただ、異動があるからこそ、常に新しいことを学び、挑戦し続けることができるとも感じています。異動のタイミングで、しっかりと次の担当者に業務を引き継ぎ、新しい部署でまた新たな気持ちでスタートを切る。その繰り返しが、自分自身の成長にも繋がっているのだと思います。
ー最後に、公務員を目指す方、糸満市役所に関心のある方へメッセージをお願いします!
上原:糸満市は、美しい海に囲まれた、人も温かい素晴らしいまちです。市役所の仕事は、税務から福祉、防災まで本当に多岐にわたりますが、その全てが市民の生活に繋がり、まちの未来を創っていく仕事です。
もちろん、大変なことや難しい課題もたくさんありますが、それ以上に「市民のために」「このまちのために」という熱い想いを持って働ける、大きなやりがいのある仕事だと思います。
主体的に考え、周りと協力しながら、前向きに課題解決に取り組める方、そして何より糸満市が好きで、このまちをより良くしていきたいという情熱のある方と、ぜひ一緒に働きたいです。
仕事をやり遂げて、庁舎の窓から一緒に綺麗な夕日を眺められる日を楽しみにしています!

ー本日はありがとうございました。
取材・文:パブリックコネクト編集部(2025年4月取材)



