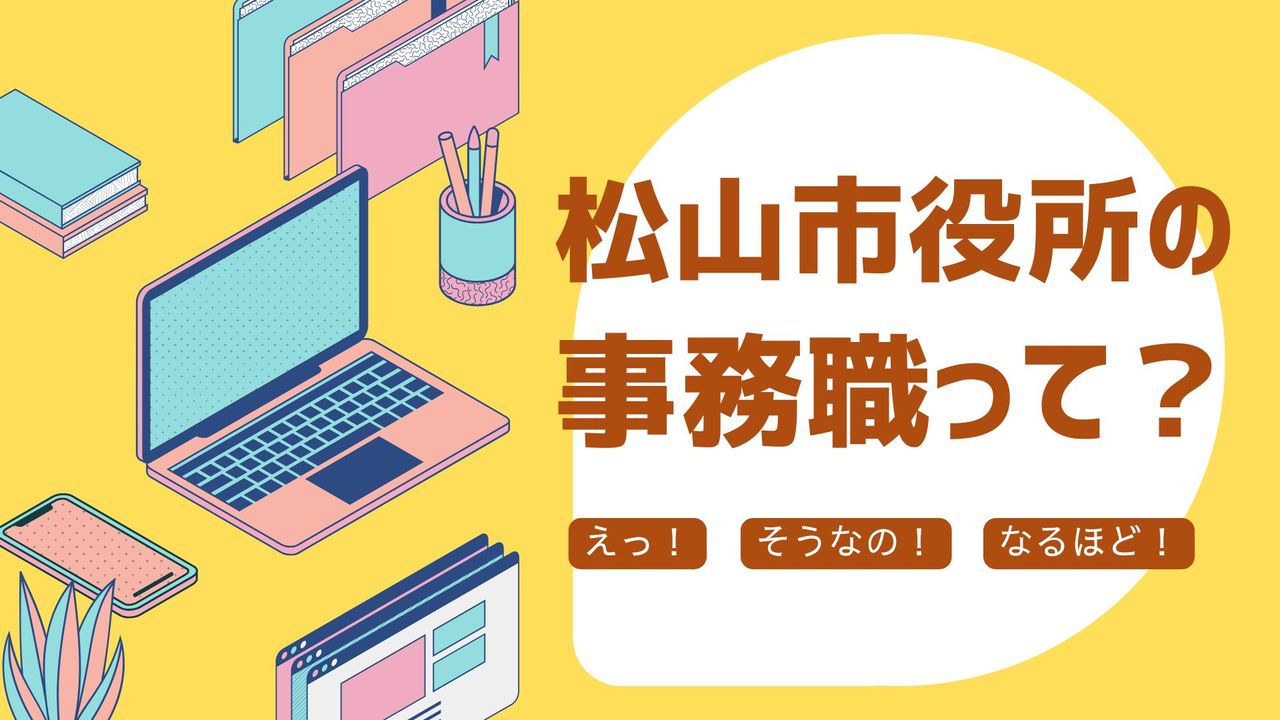今回は、公務員への就職を考え始めたあなたに「松山市役所の事務職」についてわかりやすくお伝えします。これを読めば、松山市役所でどんな仕事が行われているのか、まずは概要をつかむことができます!
「市役所の事務職は、どんな仕事をしているのですか?」
合同就職説明会の場などで、よく聞かれるこの質問。これは、公務員志望の方が最初に気になるポイントですよね。実は、この質問に答えることは、結構難しいんです。
担当者が具体的な経験に基づいて答えることはできても、市役所全体の仕事をひとくちで説明するのは至難の業!どうしてかというと、松山市役所の仕事の幅がとにかく広いからです。
なんと松山市役所には100以上の部署があります!働く事務職員は、3~5年ごとの異動を繰り返して色々な部署を経験していきます。ベテラン職員でも10部署を経験していれば「かなり多い方!」と言われるほど。
それでは、松山市役所・事務職の仕事を、わかりやすく、シンプルに説明していきます。
事務職を目指す方は必見です!
まずは全体像を見てみよう!
まずは「市役所がどんな組織なのか」を理解しましょう。松山市役所内の組織は、大きく分けると「部」という単位があり、その中にさらに細かい「課」があります。
同じ目的の仕事や似た仕事を集め、組織(課)の大きさを適正な規模にして、仕事を効率的に進めていくために、このような体制となっています。
今回は、部よりも大きな枠組みで市役所の事務職の仕事を解説していきます!
まず、市役所の課を大まかに分類すると、以下の3つの分野に分けることができます。
(1)市民の生まれる前から、亡くなるまでに関わる仕事
(2)市民の安全・安心に関わる仕事
(3)まちの活力に関する仕事
分類ごとに徹底解説!
(1)市民が生まれる前から、亡くなるまでに関わる仕事
今回の3つの分類の中では、最も多くの職員が働いている分野です。
松山市役所には正職員の事務職が約1,800人いますが、このうち約750人がこうした市民のライフイベントに関わる業務に従事しています。
例えば、以下のような課と仕事があります。
- 市民部市民課│出生届、戸籍、住所変更、死亡届
- 福祉推進部健康保険課及び保険給付・年金課│医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度)
- 健康医療部健康づくり推進課及び保健予防課│がん検診、予防接種
- こども家庭部すくすく支援課及び子育て支援課│妊娠届、児童手当、子ども医療助成
これらの課では、来庁した市民を応対する場面が多いです。法律で定められた手続きを、正確かつ迅速に、そして市民の要望に寄り添って提供することが求められます。
さらに、この分野の仕事は法律に基づく事務が中心なため、提供するサービスの内容自体に全国的に大きな違いはありませんが、自治体独自の取り組みを展開できる場合もあります。松山市では、市単独の財源で行う事業や、国の制度の中にも松山市ならではの工夫を凝らしたものもあります。このような独自の取り組みは、市民の声を直接聞く機会が多い市役所だからこそ実現できると言えるでしょう。
市民課の「ワンストップサービス」は松山市役所の大きな特徴 例えば、市内での引っ越しの場合、従来であれば市民課で住所変更をした後、さらに保険や年金の担当課でも住所変更手続きを行う必要がありました。ワンストップサービス導入後は、市民課だけで全ての手続きを完了できるため、市民の皆様は複数の課を回る煩わしさがなくなりました。
当然、対応する職員は、100種類以上の手続きに対応するための知識と経験が求められ、大変な面もあります。それでも市民の皆様からは好評で、市民サービスの向上につながっています。
|

「市民が生まれる前から、亡くなるまでに関わる仕事」のポイント
|
(2)市民の安全・安心に関わる仕事
次にご紹介するのは、近年特に力を入れている「市民の安全・安心」に関する仕事です。この分野は、災害への備えからインフラの維持まで、私たちの生活に密接に結びついており、支えている職員たちの努力が暮らしの安定を作っています。
具体的には、
- 防災・危機管理:災害が発生した又は発生しそうなときに、災害対策本部を設置し、被害を少なくするために、すぐに対応できるようにしています。また、平時から、防災計画の策定や避難対策など、被害が最小限になるよう取り組んでいます。また、松山市の防災士数は、全国で初めて1万人を突破したほか、産官学民が連携した「切れ目のない全世代型防災教育」に取り組み、様々な世代や職域に応じた防災教育を進めています。
- 上下水道などのインフラ:いつも当たり前に利用できている上下水道。当たり前を維持するために事務職のほか、土木技師、電気技師、機械技師といった専門職が連携して業務に当たっています。上下水道は特別会計で、水道料金や下水道使用料の管理や、持続可能な水道や下水道の経営のために、適切な投資と財源のバランスを日々はかっています。日々の運営から長期的なインフラ整備まで、市民生活の基盤を守るための努力が続けられています。

これらの分野で、特徴的なのは、「多職種が連携して取り組む仕事」であるという点です。具体的には、以下のように、事務職と専門職が協力しています。
例えば、
- 防災危機管理部:消防職、土木技師、建築技師、保健師
- 上下水道部:土木、電気、機械、化学技師
などの職種と事務職が一緒に協力して働いています。
松山市内という限られたエリアの中で、職員間の距離が近い中で働くからこそ、他職種と密接に関わりながら事業に当たることができます。

職種が違えば、価値観が違い、課題に対するアプローチの考え方が異なることもあります。こうした場合でも、松山市職員は、「話せば理解、話さなければ誤解」というマインドを持って、積極的に異なる考え方を議論させながら、市民生活がより良くなるよう努めています。
「市民の安全・安心に関わる仕事」のポイント
|
(3)まちの活力に関する仕事
地域資源を活用したまちづくりや地域活性化は、全国の地方公共団体でも取り組まれている分野ですが、それぞれの地域固有の資源を最大限に活用することで、独自の特色が際立つ側面があります。松山市役所でも、地域の魅力を生かしたまちづくりに力を入れている部署が多数存在します。
例えば、松山市役所の取組としては、
坂の上の雲まちづくり部=松山市ならではの部で、独自の資源を生かして、まちの活性化を図っている部署です。

- まちづくり推進課:小説『坂の上の雲』の主人公3人が抱いた高い志とひたむきな努力、夢や希望をまちづくりに取り入れたのが『坂の上の雲』のまちづくり。市内全体を屋根のない博物館に見立てた「フィールドミュージアム構想」を掲げていて、その作品となる小説ゆかりの史跡や地域固有の資源を行政と市民が一緒に見つけ、活用し、結びつけることで、回遊性の高い物語のあるまちづくりを進めています。
- 文化・ことば課:松山の夏の風物詩となっている「俳句甲子園」や「坊っちゃん文学賞」など独自性の高い事業に取組み、俳都松山や文学のまちを広く発信。令和8年夏には、正岡子規と夏目漱石が松山で52日間の共同生活をした「愚陀佛庵」を再建します。

- スポーティングシティ推進課:スポーツを「する」、「みる」、「ささえる」機会を創出し、市民が心身の健康を実感できるまちづくりを進めています。具体的には、プロ野球公式戦の開催や、地域に密着したプロスポーツ(愛媛FC、愛媛マンダリンパイレーツ、愛媛オレンジバイキングス)支援事業のほか、各種スポーツ大会・合宿等の誘致に取り組んでいます。

※このほか産業経済部や農林水産部も地域の特色が出やすい分野です。
「まちの活力に関する仕事」のポイント
|
まとめ
松山市役所の事務職は、市民の生活に寄り添いながら、地域社会を支える重要な役割を担っています。
日々の窓口対応や行政手続きだけではなく、市民の声を受け止め、それを形にする政策や地域づくりまで、広範囲にわたる業務に従事しています。
事務職として積み重ねられる一つ一つの仕事は、市民の暮らしを支える基盤を作り、松山市の未来に貢献するものです。
このブログをきっかけに、そんなやりがいある仕事の魅力を感じていただけたなら嬉しく思います。
そして、より詳しく松山市役所の業務について知りたいという方は、ぜひ松山市役所業務説明会や合同就職説明会などで、実際に各現場で働いている職員の生の声も聞いていただければと思います!
詳細が決まりましたら、松山市職員採用情報サイト(本サイト)でもお知らせしますので、ぜひご参加ください!