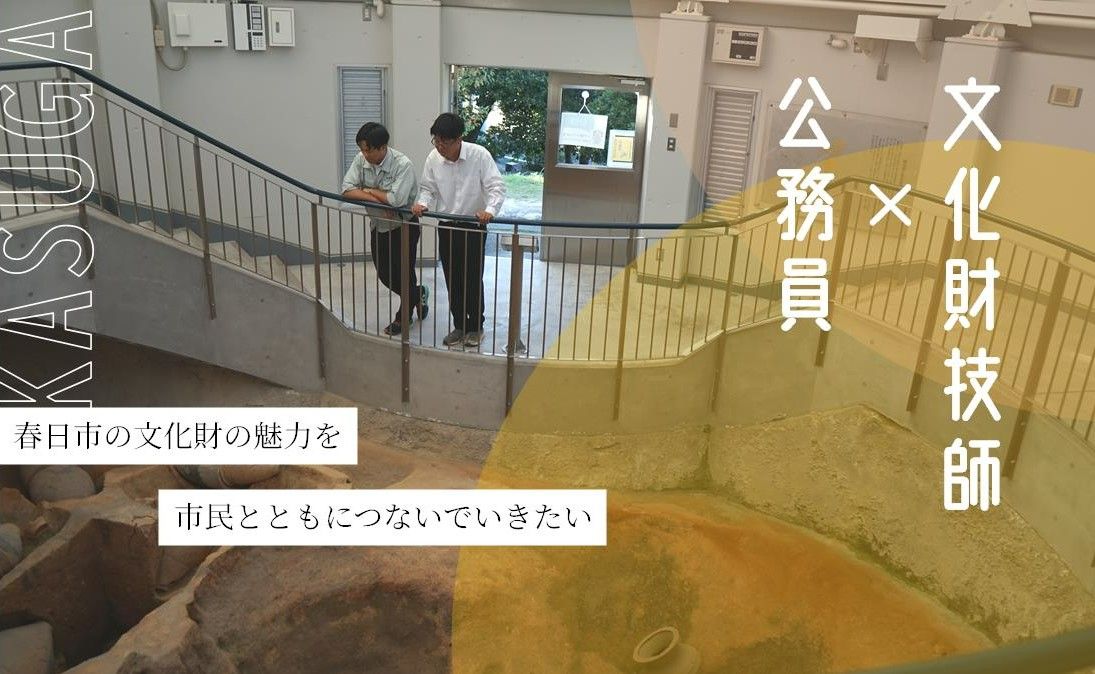幼い頃からの歴史への興味と、「地域に貢献したい」という強い思いを胸に、春日市役所の文化財技師の道を選んだ石本さんと重野さん。
彼らが働く春日市は、古代の「奴国」の首都とされる地であり、全国的にも世界的にも貴重な遺跡が豊富に眠る、まさに歴史の宝庫です。
今回は、歴史のフィールドで活躍する二人の若手文化財技師に、春日市を選んだ理由、仕事の醍醐味、そして文化財技師を目指す未来の仲間へのメッセージを伺いました。
入庁までの軌跡
ーまずは、お二人のこれまでの道のりをお聞かせいただけますか?
石本:私は福岡県太宰府市出身で、大分県内の大学で考古学を専門に学びました。就職活動では公務員を中心に受け、特に発掘調査や考古学に携われる分野を志望していました。
公務員であれば、遺跡の調査や歴史活用事業を主体的に行えると感じたことが、この道に進む決め手となりました。
重野:私は福岡県広川町の出身です。京都府内の大学で歴史を専攻し、小学生が主体となって、歴史見学で学んだことや文化財の魅力をまとめたマップを作ったり、動画を制作したりして魅力を発信するプロジェクトに力を入れていました。
就職活動では公務員と民間企業を半々で考えていましたが、子どもたちに歴史の魅力を伝える事業に携わりたいという思いから、公務員を強く意識するようになりました。

春日市を選んだ理由と採用試験の内容
ー数ある自治体の中で、春日市を選ばれた理由を教えてください。
石本:就職活動の中で、春日市が【コミュニティスクールを通じた子ども向けのイベントや、文化財の活用事業に非常に力を入れている】ことを知りました。
自分もそうした活動に主体的に携わりたいという強い思いがあり、春日市を志望しました。また、実家のある太宰府市に近かったというのも大きいですね。
重野:春日市を選んだのは、まず【その土地に眠る文化財の豊かさ】に魅力を感じたからです。全国的にも世界的にも価値のある貴重な遺跡が、このコンパクトな市内にたくさん詰まっています。
そして、それ以上に【その文化財の魅力を伝えられる子どもたちが純粋に多い】という点に惹かれました。
約11万人が暮らす春日市には、多くの小学生や中学生がおり、彼らに歴史の面白さを伝えるのに最も効果的な場所だと感じたんです。

ー採用試験はどんな内容でしたか?また、面接の雰囲気はいかがでしたか?
石本:採用試験は、一次がSPI試験で、二次がオンライン面接、三次が専門試験・実技試験・面接、四次が小論文・面接といった選考フローでした。実技試験は、発掘調査で出土した土器を実測するというものでした。
重野:採用試験の面接では、独特の緊張感がありました。
特に二次面接はオンラインでのグループ面接でしたので、「受験者が多数いる中で、いかに自分をアピールするか」を考えて臨みましたね。
三次の対面グループ面接では、市役所の幹部職員や文化財課の専門家の方々が面接官となり、専門知識と行政としての視点、双方からの質問が織り交ぜられました。
そして最後の個別面接では、多数の面接官を前に「なぜ春日市なのか」「春日市でどんなビジョンを描くのか」といった深い部分まで問われ、改めて自己と向き合う貴重な機会となりました。
文化財技師の仕事の醍醐味とやりがい
ー現在の具体的な業務内容について教えてください。
石本:私は文化財課の「調査保存担当」に所属しており、主に遺跡の発掘調査、出土した文化財の活用・展示、そして調査報告書の作成に携わっています。
非常に多くの現場が稼働しており、ほぼ年間を通して現場に出ていますが、展示の準備などは数ヶ月前から始まることもあります。


重野:私も同じく文化財課で、「整備活用担当」に所属しており、課内の全般的な庶務、窓口対応、歴史資料館の見学対応、そしてイベントや企画展の運営を担当しています。
特に、歴史資料館には年間数千人もの小中学生が学習の一環で訪れてくれます。


ー仕事の中で、特にやりがいを感じるのはどんな時ですか?
石本:この仕事のやりがいは、やはり【歴史の最前線】で新しい発見ができることです。
発掘調査を通して、今まで知られていなかった事実や貴重な遺物に出会える瞬間は、何物にも代えがたい喜びがあります。
また、現地説明会などで市民の方々が私たちの仕事や考古学に興味を持って話を聞いてくださる時、自分たちのやっていることの魅力がより伝わったと感じ、達成感を覚えます。

重野:この仕事の醍醐味は、一般事務とは異なる【歴史という独自の視点】から市民の皆さんにアプローチし、文化財を支え、未来へと継承していけることです。
その中でも特に印象深いのは、毎年9月末に開催される「弥生の里かすが奴国の丘フェスタ」という一大イベントの運営ですね。
2,000人を超える来場者が訪れるこのイベントは、歴史に関わる様々な体験を通して文化財の魅力を伝えることを目的としています。
イベント準備は綿密で、担当内での密な連携が求められ、運営の難しさを痛感しました。
しかし、当日、多くの方が楽しんで帰られる姿を見ると、本当に「イベント運営ってこんなに楽しいんだ!」と感じ、大きなやりがいを得られます。
仕事のリアルと働く環境
ー逆に、仕事で大変なことや苦労したことなど、「厳しさ」の面はいかがですか?
石本:文化財技師の仕事は、学生時代に学んだ専門知識以上に、幅広いスキルや深い知見が求められると感じています。日々新しいことを学び続けるのは大変な部分もありますね。
また、私たちは夏場や冬場でも外での現場作業に当たることが多く、特に夏場の現場は過酷です。体調管理や熱中症対策には、常に気を遣っています。
重野:私の業務で大変なのは、専門的な文化財業務から一般事務、さらには大規模イベントの運営まで、非常に幅広い分野の業務を【マルチタスクでこなす必要性があること】です。
ですが、これは様々な経験を積ませてもらえる機会でもあると捉えています。

ー職場の雰囲気やワークライフバランスについてお聞かせください。
石本:ワークライフバランスについては、夏季休暇はしっかり取得できていますし、学会への参加のために休みを取ることもあります。
しかし、現場が始まると月曜日から金曜日まで業務がびっしりと詰まるため、休暇を取ることができない時期もあります。
職場の雰囲気は、現場では非常に賑やかで楽しく、先輩技師や発掘作業員の方々からたくさんのアドバイスをもらいながら業務を進めています。

重野:ワークライフバランスに関して言えば、私の担当部署は他の部署に比べて残業は比較的少ない方だと感じています。
しかし、イベント対応などのため、休日の出勤は多くなる傾向がありますが、その分、代休はきちんと取得できる体制が整っており、柔軟な働き方ができています。
職場の雰囲気は、一見すると静かな部署に見えるかもしれませんが、実はお茶目な人が多く、とてもアットホームです。困った時はみんなで助言やサポートをしてくれますし、一緒に作業をしようと提案してくれる先輩もいます。
同期は私やここにいる石本さんを含め13人いますが、非常に仲が良く、仕事の愚痴や趣味の話で盛り上がったり、休日に一緒に出かけたりすることもあります。

未来を担う文化財技師へのメッセージ
ー最後に、春日市の文化財技師として働く魅力と、これから就職・転職を考えている方へのメッセージをお願いします。
石本:春日市は何よりも非常に貴重な文化財が豊富に眠っていることが最大の魅力です。
新聞記事になるような遺物や遺跡が次々と見つかることも珍しくなく、古代の「奴国」の首都とされたこの地で、発掘調査の最前線に立てることは、文化財技師として最高の経験だと感じています。
文化財や考古学に強い興味と関心があり、それを深く掘り下げていきたい方にとって、春日市は非常にやりがいがあり、学びの多い職場だと確信しています。
ぜひ私たちと一緒に、春日市の歴史を未来へ繋ぐ仕事をしていきましょう。
重野:春日市は、全国的にも世界的に見ても価値のある貴重な遺跡が、コンパクトな市内に密集して存在していることが大きな魅力です。
そして、歴史のフィールドにすぐに触れることができる環境が整っていて、さらに、市民の皆さんも文化財への関心が非常に高い春日市は、文化財技師にとって最高の舞台です。
就職活動中は自己分析を重ね、自分と深く向き合う中で、困難や壁にぶつかることも多いと思いますが、ぜひ「これは自分を見つめる大切な時期だ」と前向きに捉えてほしいと思います。
そして、公務員に対して「堅苦しい」という固定観念があるかもしれませんが、それを一度捨ててみてください。
春日市は、歴史を愛し、それを多くの人に伝えたいという意欲がある方を心から歓迎します。皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしています。

ー本日はありがとうございました。
石本さん、重野さん、本日は大変貴重なお話をありがとうございました。
【歴史の最前線】で新しい発見ができる喜びや、子どもたちに歴史の面白さを伝える瞬間のやりがいを、温かい言葉で語ってくださったことに、深く感動いたしました。
お二人が春日市の文化財を守り、未来へ繋ぐ情熱に満ちた姿は、まさに地域を支える光です。
文化財技師として働くお二人の輝きが、春日市の歴史と共に、これからもずっと未来を照らし続けることを心から願っています。
取材・文:パブリックコネクト編集部(2025年10月取材)