「生まれ育った故郷に貢献したい」「インフラ整備を通じて、人々の生活を支えたい」
そうした強い想いを胸に、公務員の土木技術職という道を選ぶ人は少なくありません。
今回は、生まれ育った大和郡山市で土木技術職として活躍する安藤さんに、故郷への想い、仕事のやりがい、そして3ヶ月間の育児休暇取得という充実したワークライフバランスを可能にする、職場の「人の良さ」についてお話を伺いました。
- 土木技術職を志したきっかけと大和郡山市との出会い
- まちのインフラを支える仕事内容と業務体制
- 目に見える成果と世間の注目がやりがいに
- 充実したワークライフバランスと育児支援
- 「人の良さ」が育む、風通しの良い職場環境
- 大和郡山市で働く魅力と求職者へのメッセージ
土木技術職を志したきっかけと大和郡山市との出会い
ーまずは、入庁までのご経歴と、土木技術職を志されたきっかけについてお聞かせいただけますでしょうか?
安藤:私は大和郡山市で生まれ育ち、高校まで大和郡山市で過ごしました。大学は大阪の大学に進学し、都市工学や植物、公園整備といった分野を専攻していました。
大学院まで含めると6年間その分野に在籍し、卒業後に地方公務員として2年間勤務した後、縁あって大和郡山市に転職し、現在に至ります。
土木技術職を志したきっかけは、大学での学びが大きく影響しています。公園整備や道路整備といったインフラ系の整備に携わりたいという思いが強かったんですね。
この分野に関わる仕事としては、公務員の他に建設会社やコンサルタントといった選択肢もありますが、発注者として幅広い業務に携われる公務員という道を選びました。
ー大和郡山市への転職を決めた理由は何だったのでしょうか?
安藤:やはり生まれ育った故郷である大和郡山市に貢献したいという気持ちが一番大きかったです。ちょうど募集があったタイミングでもあり、地元のために働きたいという思いで転職を決めました。
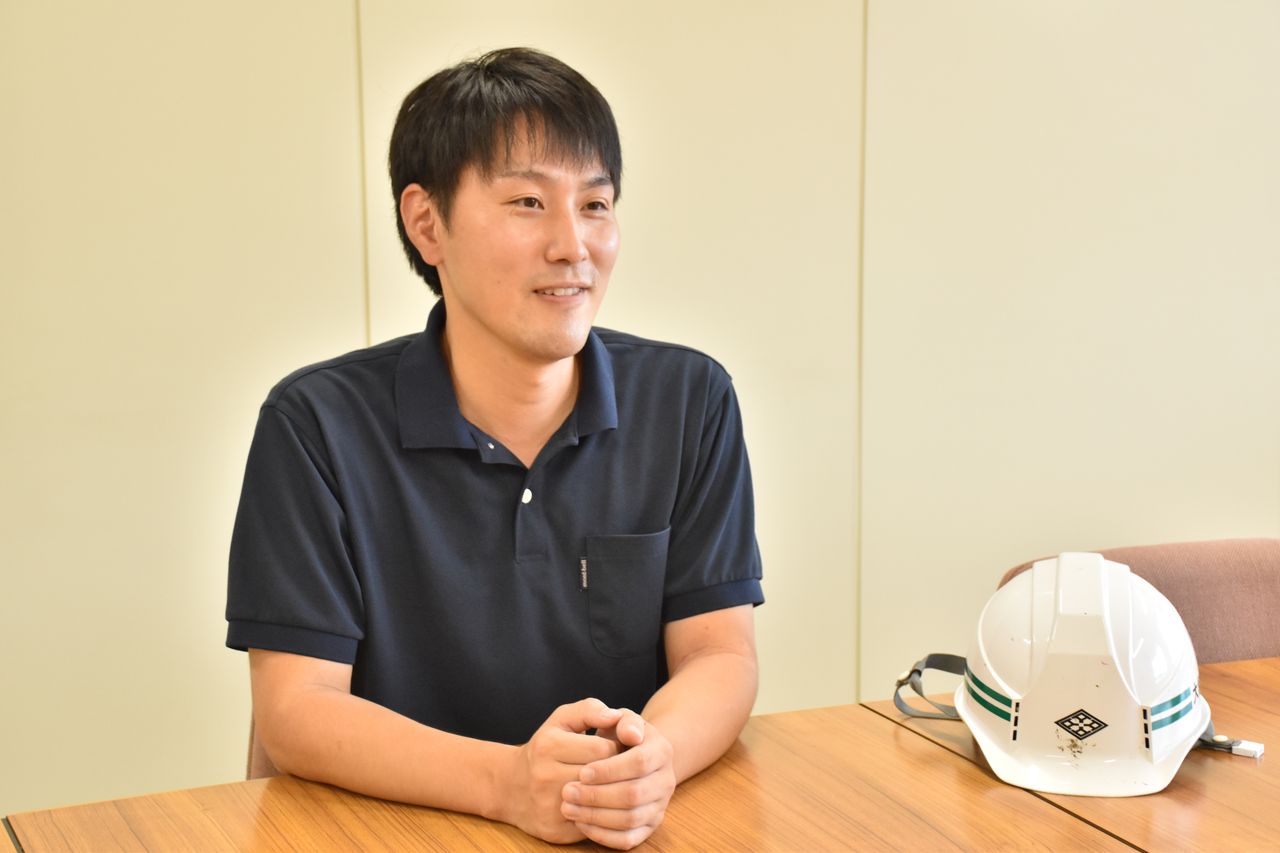
まちのインフラを支える仕事内容と業務体制
ー大和郡山市に入庁されてから、どのような業務を経験されてきましたか?
安藤:大和郡山市に入庁後は、まず建設課に5年間配属されました。最初の1年間は治水係で、大雨が降った際に一時的に水を貯める調整池の維持管理等を担当していました。
その後4年間は道路係に移り、道路の拡幅や新設工事を担当しました。具体的には、工事の設計や監督業務を行い、主に1年では終わらないような比較的規模の大きな事業を複数担当しました。
昨年度からは下水道推進課に異動となり、現在は下水道施設の維持管理が主な業務です。市民の方々や業者さんからの問い合わせや相談などに対応しています。
例えば、「マンホールの蓋がガタついている」「下水道の管が詰まって流れなくなった」といった内容ですね。自分たちで解決できる場合は直接対応しますが、専門的な工事が必要な場合は業者に発注し、その設計と監督を行っています。
対象物は、主に道路の下に埋まっている管や、道路上にあるマンホールが中心です。また、家屋内の生活排水を流す排水設備の検査なども行っています。
ー工事のサイクルについてお伺いしたいのですが、発注業務などは特定の時期に集中するのでしょうか?
安藤:下水道の維持管理業務は、道路工事のように何年もかけて計画的に進めるものばかりではありません。突発的にトラブルや苦情が発生することが多いため、その都度工事を発注し、対応していくことになります。
そのため、「この時期が特に忙しい」という特定の期間はなく、年間を通して比較的忙しく対応しているイメージですね。
もちろん、計画的に進める工事もありますので、そういったものは夏頃に発注をかけることが多く、その時期は設計書の作成などで忙しくなることもあります。

目に見える成果と世間の注目がやりがいに
ー土木技術職として働く中で、どのような時にやりがいを感じますか?
安藤:土木技術職の大きな魅力は、【仕事の成果が目に見えやすい】ことにあると思います。
例えば、道路を広げる工事を担当した場合、工事が終われば道が実際に広がり、それを利用する車や地域住民の方々の喜ぶ声が直接届きます。
下水道に関しても、管の詰まりを解消すれば水がスムーズに流れるようになるのが見て取れます。
このように、自分の仕事が具体的な形として残り、人々の生活に貢献していることを実感できると、大きな達成感を感じますね。
ーこれまでで特に印象に残っている業務や出来事があれば教えてください。
安藤:建設課時代に担当した、地域内の細い道の拡幅工事が印象に残っています。そこは車1台がやっと通れるような道で、緊急車両もスムーズに入れない場所でした。
この道を拡幅し、緊急車両も通れるようにする事業を、前任から引き継いだ後、担当者として最後までやり遂げることができました。
工事には、田んぼの持ち主の方々や水利組合など、多くの方々との調整が必要で、何年もの期間をかけて進めました。
完成後、地域の方々から「良くなったよ」「ありがとう」という感謝の言葉をいただいた時は、本当にやってよかったと心から思いましたね。
下水道推進課に移ってからは、国内で発生した大きな陥没事故に関連して、大和郡山市内の大規模な下水道管の調査業務を担当しました。
世間の注目度が高い案件に自分も関わることができたため、普段とは違う緊張感があり、非常に記憶に残っています。

ー仕事の大変さや厳しさについてはいかがでしょうか?
安藤:他の業種と比較すると、土木技術職は【突発性や緊急性への対応】が求められる場面が多いと感じています。例えば、台風などの災害が発生した際は、土木技術職が先陣を切って対応しなければなりません。
そういった意味では、「自分が地域のインフラを守るんだ」という強い気持ちや覚悟が必要な仕事だと感じています。
充実したワークライフバランスと育児支援
ー残業や休暇の取りやすさなど、ワークライフバランスについてはいかがでしょうか?
安藤:過度な残業が常にあるわけではありません。
突発的な事案が重なってしまった時など、状況によっては残業が発生することもありますが、毎日残業しているわけではないので、自分で調整すれば休暇も比較的取りやすい環境で、仕事とプライベートのバランスをうまく取りながら働けていると感じています。
ー育児休暇の取得経験についてお聞かせいただけますか?
安藤:実は昨年、子どもが生まれまして、3ヶ月間の育児休暇を取得させていただきました。休暇の取得にあたっては、もちろん職場と相談した上で、快く承認していただけました。
3ヶ月間職場を離れることになり、業務の引き継ぎなど課題はありましたが、周りの方々の多大な協力のおかげで無事に取得できました。
このような制度がしっかり整っており、それを職員が活用できる職場環境があることは、本当に素晴らしいことだと感謝しています。
「人の良さ」が育む、風通しの良い職場環境
ー職場の雰囲気や、上司・同僚との関係性についてお聞かせください。
安藤:建設課にいた頃も、今の下水道推進課も、本当に「良い人たちが多い」という印象です。困ったことがあれば、上司や先輩はもちろんのこと、後輩も含めて皆が親身になって相談に乗ってくれます。
皆が協力してくれるおかげで仕事もスムーズに進みますし、お互いを高め合えるような、非常に風通しの良い職場だと感じています。
各工事に対して主担当を一人決めていますが、決してその一人に任せきりにするのではなく、チームとして連携して取り組んでいます。
日頃から相談に乗ってくれますし、トラブルや難しい案件があった際は、上司が一緒に現場に行ってくれるので、安心して業務を進めることができていますね。
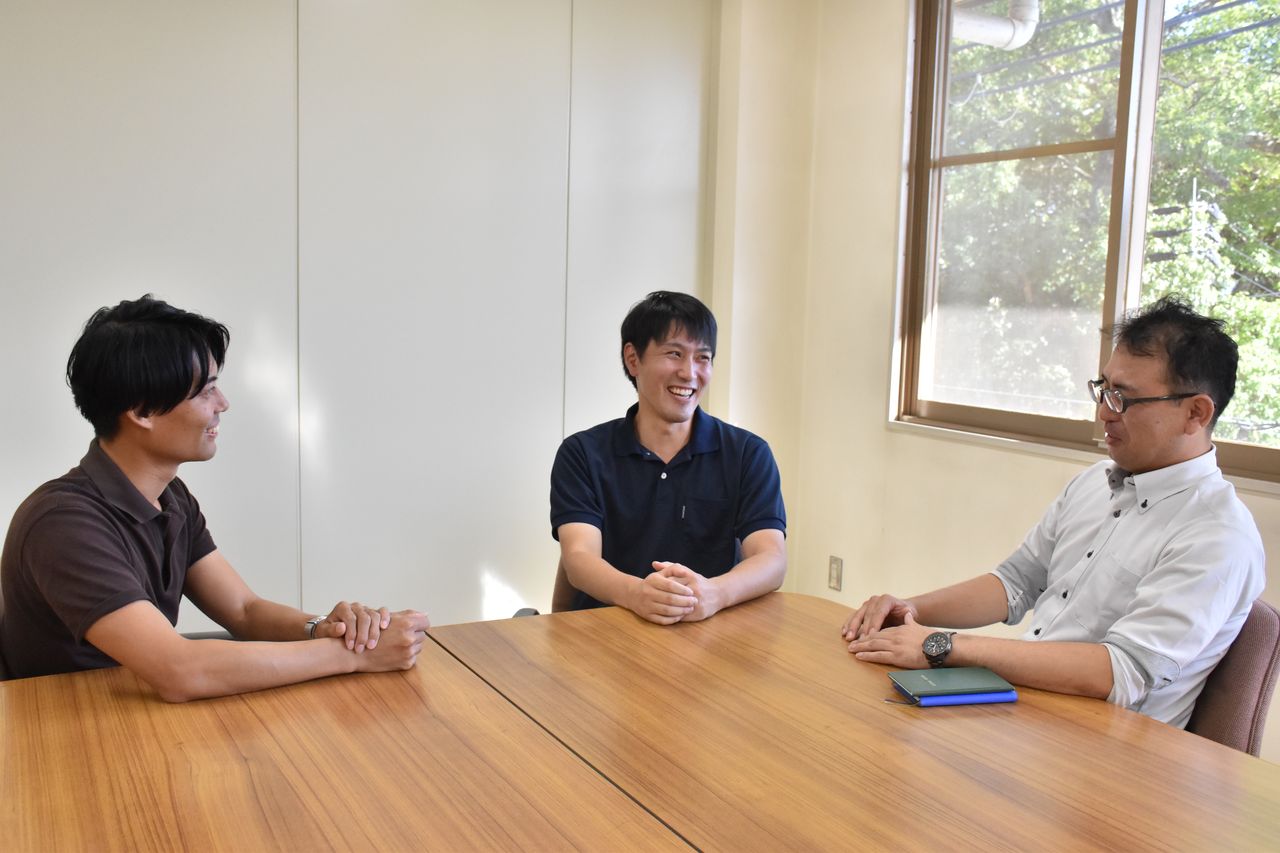
大和郡山市で働く魅力と求職者へのメッセージ
ー最後に、今後大和郡山市役所の土木技術職を目指す方々へ、メッセージをお願いします。
安藤:土木技術職の仕事内容自体は、どこの自治体でも似たようなものかもしれません。しかし、大和郡山市の一番の魅力は「人の良さ」だと感じています。これほど良い人が多い職場は珍しいのではないかと思うほどです。
また、私がこれまでお話ししてきたような「環境の良さ」や「風通しの良さ」を含めて、非常に働きやすい職場です。そういった面で大和郡山市を選んでいただけたら、「ここに入庁してよかった」と心から思えるはずです。
皆さんと一緒に働くことができる日を、私も楽しみにしています。

ー本日はありがとうございました。
安藤さんの言葉からは、生まれ育った大和郡山市への深い愛情と、技術職としての確かな誇りが感じられました。特に、細い道を緊急車両も通れるように拡幅し、地域の方々から感謝されたエピソードは、公務員という仕事が人々の生活にどれほど深く結びついているかを教えてくれました。
また、3ヶ月の育児休暇を取得されたというお話は、大和郡山市役場の職員が互いに助け合い、制度を活かせる「人の良さ」が根付いている証だと感じました。
土木技術職としての「仕事」だけでなく、「人」にも愛着を持って働けるというお話は、これから大和郡山市の職員を目指す方々の背中をそっと押すような言葉になるのではないでしょうか。
取材・文:パブリックコネクト編集部(2025年9月取材)



