野々市市の保育士として働く寺岡さんと人見さんのインタビュー記事です。大学卒業後、そして民間企業や異業種での経験を経て、お二人が公立保育園で働くことを選んだ理由とは。
「ノンコンタクトタイム」制度や、幅広い年齢層の職員が支え合う温かな職場の雰囲気、そして子育てと両立しやすい制度など、長く安心して働ける環境の魅力について、詳しくお話を伺いました。
ーまずはお二人のこれまでの経歴を教えていただけますか。
寺岡:もともと大学は教育学部でしたが、在学中に子どもたちと触れ合った経験から教員ではなく保育士を目指すこととし保育士資格を取得して、野々市市役所で嘱託職員からはじめ、正規職員として受け直し、現在に至ります。
人見:県外の短期大学で保育士の勉強をし、地元石川県の民間保育園で5年間勤務しました。その後、以前から興味があった美容業界に転職し、エステサロンで3年ほど勤めました。
そして、結婚を機に「もう一度保育士として頑張りたい」と思い、野々市市の会計年度任用職員に応募し、約2年間勤務しました。その後に正規職員の試験を受け、現在は公立保育園で正規職員として働いて3年目になります。

ーなぜ保育士として復帰される際は野々市市にされたんですか?
人見:民間の保育園で働いていた時、結婚や出産を機に辞めてしまう方を多く見てきました。一方で、公立園は長く勤めている方が多いという印象があり、将来のことを考えた時に、安心して働き続けられる環境ではないかという気持ちがありました。
ーでは、お二人は現在、それぞれ別の園でご活躍されていると伺いました。今、どのようなお仕事をされているのか、園の様子とあわせて教えてください。
寺岡:私は富奥保育園に務めています。園児数が75名ほどで、市の公立園の中では比較的小規模な園です。私は主任としての業務のほかに、今年度から始まった「ノンコンタクトタイム」を円滑に進めるための役割を担っています。
人見:私が勤めているのは定員140名の、市内では規模の大きい園です。現在は24名が在籍する4歳児クラスで、担任のリーダーを務めています。私のクラスには、個別のサポートが必要なお子さんが2名おり、それぞれに加配の先生が一人ずつ付いています。私はその先生方と連携しながら、クラス全体を見て中心的な役割を担う、という形です。
ー「ノンコンタクトタイム」とは、どのような制度ですか?
寺岡:これは、担任の保育士が休憩時間とは別に、子どもたちから完全に離れて保育の準備や書類作成に集中できる時間を確保するための制度です。例えば、人見さんのような担任の先生がいるクラスに、私が1〜2時間代わりに入ります。
その間、担任の先生はクラスを離れて、指導案を作成したり、子どもたちの姿を振り返って次の保育計画を練ったりできるわけです。そうした時間を確保することで、保育の質をさらに高めていくことを目的としています。また、私が様々なクラスに入ることで、園全体の状況を把握し、必要に応じて担任の先生に助言をすることもあります。
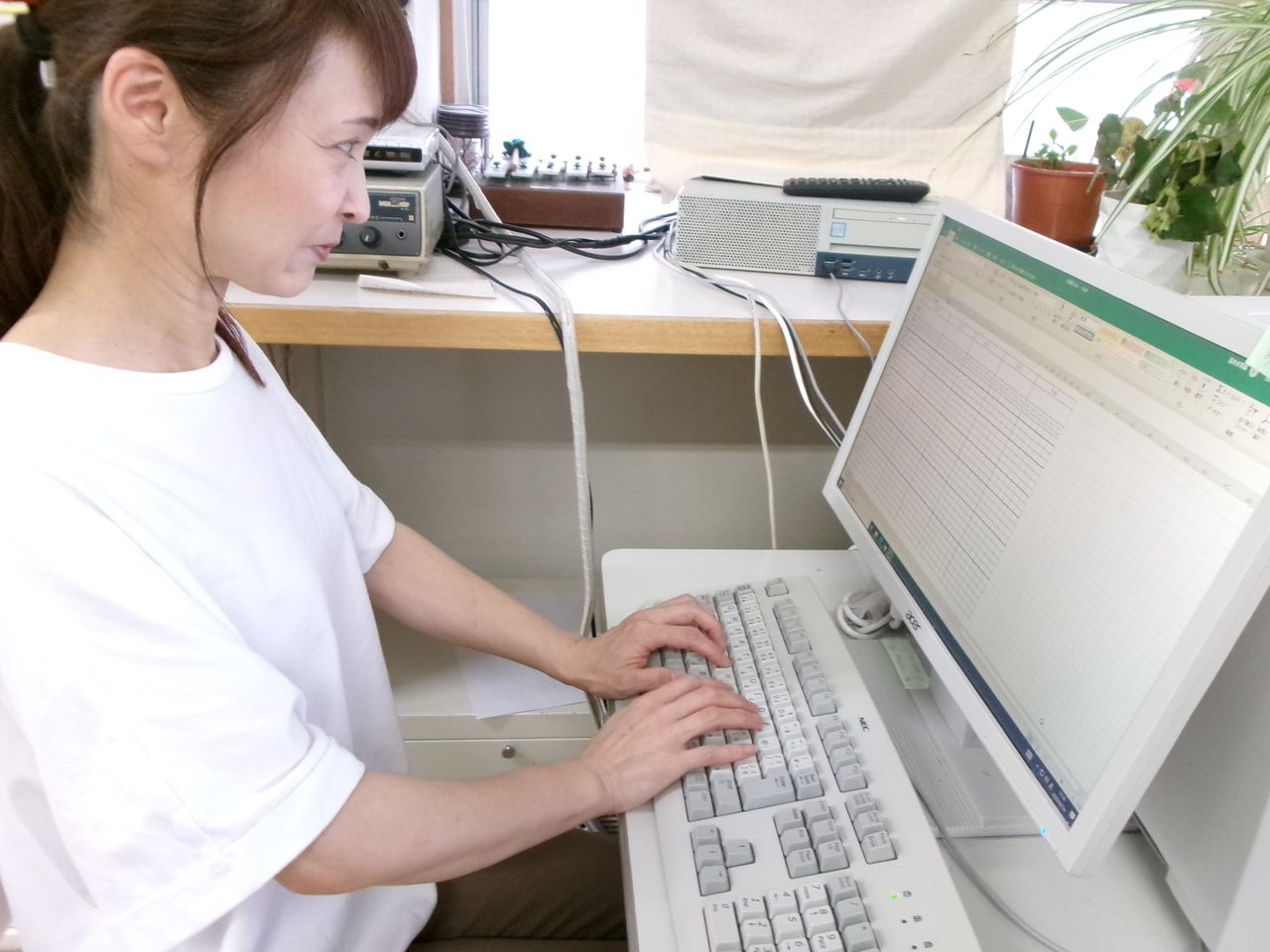
ー保育士さんの負担軽減にもつながりそうです。
寺岡:この制度は、昨年ある園で試験的に導入され、その効果が認められたことから、今年度から野々市市の全ての公立保育園で実施されることになりました。
人見:働き方は大きく変わり、本当に助かっています。正規職員になって3年目ですが、まだまだ仕事に慣れない部分もあり、書類作成に時間がかかってしまうこともあります。また、お昼の時間には、保護者向けのアプリでその日の活動の様子を写真付きの記事で配信したり、日誌を書いたりと、やるべきことがたくさんあります。行事前には先輩と相談する時間も必要ですが、これまではなかなかまとまった時間を確保するのが難しかったんです。
でも、ノンコンタクトタイムができたことで、計画が立てられ、実際に残業する時間も減りました。業務が軽減されただけでなく、心にも時間にもゆとりが生まれて、より質の高い保育を実践できているという実感があります。
ーそれは素晴らしいですね。野々市市の公立保育園全体で、何か共有している保育方針のようなものはあるのでしょうか。
寺岡:はい、野々市市の公立園では、私が就職した当時から「心身ともにたくましい子」という大きな目標を掲げています。これは、心も体もたくましい子を育てるという理念で、その中にはさらに5つの具体的な目標があります。
「明るくたくましい子」「考え工夫する子」「思いやりのある子」「自分なりに力を出せる子」「喜んで食べる子」の5つです。これはどこの公立園に行っても共通の目標で、この目標に向かって、皆が同じ気持ちで保育を進めています。もちろん園ごとのカラーはありますが、根底にある思いは統一されています。
ーその方針を、園を越えて共有したり、保育の質を高め合ったりする機会はあるのですか?
寺岡:「野々市市保育士会」という保育の質を高め、職員同士の絆を深めることを目標とした団体があり、その集まりの場において保育の理念などを共有しています。保育士会の中には、「保育研究委員会」「食育委員会」「乳児委員会」などの委員会があります。
例えば保育研究委員会では、月に一度、各園の代表者が集まります。数年ごとにテーマを決めて、「心身ともにたくましい子を育むために、私たち保育士に何ができるか」を話し合います。例えば「生活習慣を見直す」というテーマで各自の取り組みの情報交換をし学び合います。そこで得た情報を自分の園に持ち帰り、職員全員にも共有されます。
その他にも、講師の先生をお招きして、代表者だけでなく多くの職員が参加できる研修会も年に4〜5回開催されており、市全体で保育の質を高めていこうという意識が非常に高いです。

ー民間と公立の両方で保育を経験された人見さんから見て、公立園に入って感じたギャップや、働いてみて良かったと感じる点はありますか?
人見:民間の保育園は、園ごとに特色や強みがはっきりと打ち出されていることが多いですよね。でも公立園の場合、市内に4園あることは分かっていても、どこに配属されるか分かりませんし、入る前はどんな雰囲気なんだろうという不安は少しありました。
実際に働き始めて一番に感じたのは、職員の年齢層が非常に幅広いことです。民間の園は20代〜30代の職員が中心でしたが、今は若い職員からベテランの先生、朝夕の短時間勤務の方まで、本当に様々な世代の方がいます。自分にとってみれば、経験豊富な先輩方が仕事でつまずいた時にも的確なアドバイスをくださるのが温かいです。アットホームですし話しづらいとも感じることはないですね。
最初は私も会計年度任用職員でのスタートですが、このような環境だとわかったことで、長く働きたいという思いに至り正規職員採用募集に応募しました。

ー寺岡さんは、主任として後輩の指導にあたる立場でもあります。様々な年代の職員と関わる上で、何か意識されていることはありますか?
寺岡:何かを伝える時には、まず相手の良いところを見つけるようにしています。いきなり注意点ばかりを指摘しても、相手は受け入れにくいですよね。ですから、まずは「この間の子どもとの関わり、すごく良かったね」「子どもたち、楽しそうだったよ」といったポジティブな会話から入って、関係性を築くことを大切にしています。
その上で、子どもの成長のために伝えるべきことは、たとえ相手にとって少し耳が痛いことであっても、きちんと伝えるようにしています。一方で、若い先生たちから学ぶことも本当に多いです。発想が豊かですし、アドバイスに対して翌日にはすぐに試してくれるフットワークの軽さもあります。
そういった点で学びは私にもありますね。子どもたちが「保育園に来るのが楽しい」と思えるように、まずは私たち職員が楽しく働ける環境であることが大切だと思っています。
ー他に、野々市市で保育士として働く魅力があれば教えてください。
寺岡:福利厚生がしっかりしていて、ライフステージが変わっても働き続けやすい環境が整っている点です。子どもの看護休暇や、産前産後休暇、育児休暇はもちろんですが、「短時間勤務制度」もあります。これは、子どもが小さいうちは、正規の勤務時間(8時半〜17時15分)の前後で最大2時間、勤務時間を短縮できる制度です。この制度を利用して、子育てと仕事を両立している職員がたくさんいます。結婚や出産を経ても、安心してキャリアを継続できるのは大きな魅力だと思います。
人見:私は、野々市市という「街」そのものに魅力を感じています。私は園から歩いて3分ほどのところに住んでいるのですが、地域の方々との繋がりがとても温かいんです。よく「住みよさランキング」で名前が挙がりますが、実際に住んでみてその意味がよく分かります。
町内会で花の苗の無料配布があって、みんなで街を花でいっぱいにしようという活動があったり、夏には「じょんからまつり」という大きなおまつりに向けて地域が一体になったり。園で畑仕事をしていると、近所のおじいちゃんやおばあちゃんが「こうするといいよ」と教えに来てくださることもあります。こうした人と人との温かいつながりの中で子どもたちを育てられること、そして自分自身もその一員として働けることに、大きな喜びとやりがいを感じています。
ー本日はありがとうございました。
取材・文:パブリックコネクト編集部(2025年7月取材)



